
親族・身内が亡くなった際にほぼ必ず発生するのが、相続に関する問題です。
故人の所有していた財産を親族で分け合うことを相続といいますが、個人が相続における配分を遺言状などの形で残していれば相続は比較的スムーズに進みます。
また、あらかじめ相続の対象となる財産がどれだけのものであるか把握できていれば、相続が行き詰まる可能性も減らせるでしょう。
ですが、遺言状がない上に故人の財産の全容が明らかでない場合、もし急に多額の隠し資産や知られてなかった土地の所有権があると判明すると、残された遺族がこれらの財産をどのようにして分割するかで遺族間の争いの引き金になりかねません。
他にも、故人の借金も相続財産とみなされるため、故人の死後に遺族が突然多額の借金を抱えてしまうというケースも十分にあり得ます。
こういった無用なトラブルを避けるために、探偵による相続財産の事前調査が必要です。
この記事では、相続によって発生しがちな問題とそれらの解決に向けて探偵が行なうアプローチについて紹介します。
相続によって発生する問題とは?

まずは、故人の財産相続によって発生しがちな問題にどのようなものがあるか認識しておくことで、対策をより現実的なものと認識できます。
相続にまつわる問題の代表例を解説します。
遺産分割の割合
もっとも起こりがちな遺産相続に関するトラブルとしては、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを決めることです。
特に遺言状などによって故人の相続に関する意思が示されていない場合、基本的には故人(被相続人)の配偶者とその血族が法定相続人となります。
法定相続人の一覧・相続順位
- 故人の配偶者・子ども
- 故人の親
- 故人の兄弟姉妹
そのため、遺言などによって故人の財産分与に関する意思が確認できなければ、この法定相続人の相続順位に基づいて財産の分割が行なわれる形になります。
しかし、もし故人に養子がいる場合は子どもと同じ扱いになるため相続順位1位となり、故人の死後に明らかになった内縁関係の妻との間の子どもにも相続人となる権利が持てる場合があります。
また、遺言がない場合での法定相続人による相続における財産分与の割合は、民法第900条において規定されています。
- 配偶者と子どもが相続人の場合…配偶者と子どもで1/2ずつ
- 配偶者と親が相続人の場合…配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
- 子どもと親または兄弟姉妹複数人の場合…全員均等の割合
(父母の一方のみが同じの兄弟姉妹は、父母の双方を同じの兄弟姉妹の相続分の1/2)
法律上はこのように分割における規定がされていますが、実際に起きる相続トラブルにおいては法律上の規定が守られるとは限りません。
財産分与の割合について文句をつけるだけでなく、既に受けている生前贈与分をないものとしてきたり介護をしていた相続人の寄与分を認めないなどのトラブルがあるといわれています。
また、相続人全員の合意があれば民法第900条の規定とは異なる形での遺産相続も可能ですが、この合意を強引ややり方で迫ることも考えられるでしょう。
他にも、故人の生前に自分に都合のいい遺言状を書かせたり親族以外の人間を相続の話に混ぜるなど、民法第900条は完全な形で機能しているとはいえないのが実情です。
相続税の支払い
遺産相続とはただ残された財産を受け継げば終わる話ではなく、相続した財産を得た際にも「相続税」と呼ばれる税金が発生し、支払いの義務が課されます。
相続税の支払いは、原則として相続の発生から10カ月以内に現金での納付が求められるため、多額の財産を相続した場合は相応の相続税を支払う必要が出てくるでしょう。
もし相続財産が建物や土地といったすぐに現金化しにくい不動産であれば、相続税の支払いはさらに難しさを増すことになります。
平成27年1月の相続税法の改正によって相続財産にかかる税金はさらに重くなり、今後も相続税が増税される可能性は存在します。
対策としては、そもそもの相続財産を減らすことでかかる税金額を削ったり、不動産などであれば評価額を下げて財産としての価値を減らすことが有効です。
相続財産の分割割合を決める際には、遺族間の相続税の支払い能力についても話を詰めておく必要性もあるでしょう。
借金の相続
相続の対象となるのは故人の所有していたすべての財産になりますが、それらの財産は価値のあるものだけとは限りません。
故人が生前に抱えていた借金などの負債も相続の対象となるため、場合によっては故人の死後から多額の借金を抱えるというケースも十分起こり得ます。
しかし、相続においては相続放棄を行なうことができ、相続開始を知った時から3カ月以内に手続きを行なえば借金の相続を防ぐことが可能です。
ただ、故人が借金を抱えていたことを知らないと相続放棄を行なえないため、気づかない内に相続放棄の期限が切れて借金の取り立てが来てから初めて借金の存在を知るケースも考えられます。
そのため、遺族間のスムーズな財産分与と相続しない財産の見極めのために、相続財産の事前調査が必要になるのです。
相続のために準備すべきこと
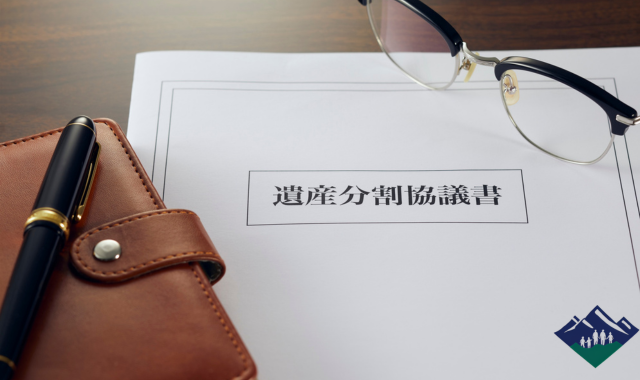
トラブルなくスムーズな遺産相続を実現するためには、準備すべきことはいくつも存在します。
これらの内容を把握した上で遺産相続に取り組めば、後々起こり得る混乱も減らせるでしょう。
生前の内に相続について話を進めておく
相続においてもっとも重要視されるのは、故人が抱く相続の意思です。
故人の意向が反映された相続割合であれば、相続トラブルが起きる可能性を減らすことも可能になるでしょう。
そのため、生前の内から被相続人を交えて遺産相続に関する話を進めておくことが何よりも重要です。
しかし、被相続人本人が遺産相続の話に乗り気でない場合、相続の進展が遅れることも見込まれます。
相続財産となるものを把握しておく
どのような種類の財産が相続の対象となるのかは、必ずあらかじめ把握しておきましょう。
相続対象になるのは現金や不動産など価値を持つプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産もありますのでその分類は覚えておくべきです。
プラスの財産
- 現金、預貯金
- 損害賠償請求権
- 知的財産権(著作権など)
- 被相続人が受取人の生命保険金
- 動産(自動車、貴金属、骨董品など)
- 不動産(土地、建物)およびその権利
- 有価証券(株式、債券、投資資産など)
マイナスの財産
- 借金、ローン
- 税金、未払いの医療費
- 保証債務
- 損害賠償債務
目に見える財産だけでなく法律上の権利も相続対象となるため、必要でないマイナスの財産については速やかに相続放棄を進めるのがおすすめです。
また、故人が死亡した際に得られる生命保険金なども「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
探偵に相続財産調査を依頼する
もし被相続人が相続遺産について話そうとしなかったり、既に故人となってから相続について考え始める場合、個人が所有していた財産の全容把握が非常に困難になります。
そうなった場合、予期していなかった金額の相続税支払いや、相続放棄が間に合わずにまったく身に覚えのない借金をいきなり抱えるといった金銭トラブルが発生する可能性があります。
また、相続をめぐっての親族間の争いが発生して法律上のトラブルにまで発展することもあるでしょう。
そのような事態を避けるためには、探偵など調査のプロによる相続財産の調査を依頼するのがおすすめです。
探偵による独自のネットワークを活用することで隠された財産や借金の存在を明らかにして、多額の相続税の発生に備えた準備ができたり適切なタイミングでの相続放棄といった対処が可能になります。
遺産相続にまつわるトラブル回避のために、まずは探偵への無料相談から始めてみましょう。


