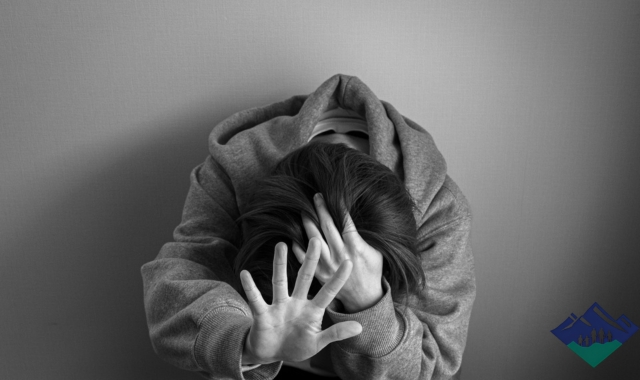
いじめは、グループやコミュニティがあるところにはどこでも生じる可能性がある問題です。
いじめという言葉を聞くと、子ども同士のトラブルを思い浮かべる人も多いですが、大人の社会でもいじめ問題は起こり得ます。
自分自身がいじめの被害者になったとき、家族や親しい人が被害者となったとき、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
この記事では、子どもによるいじめと大人によるいじめの違いや具体例についてまとめ、いじめの解決策について解説しています。
いじめの定義

そもそも、いじめとはどのようなものを指すのでしょうか。
文部科学省は、子どもによるいじめの定義について、昭和61年、平成6年、平成18年と、それぞれ若干異なる内容を発表しています。(文部科学省「いじめの定義の変遷」より)
このことから、いじめの定義は時代の流れとともに変化していることがわかります。
現在では、平成25年に施行された「いじめ防止対策推進法」に記載されている定義に統一されています。
子どもによるいじめ
いじめ防止対策推進法第2条によると、子どもによるいじめは以下のように定義されます。
「いじめとは、児童や生徒対して、その児童や生徒と一定の人的関係にある他の児童や生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」
これに加え、いじめの中には、
-
犯罪行為として取り扱うべきと認められるケース
-
早期に警察に相談することが重要なケース
-
児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なケース
が含まれています。
このような重大ないじめが発覚した場合、学校は、教育的な配慮や被害者の意向を配慮したうえで、 早期に警察に相談・通報し、警察が連携した対応を取ることが必要とされています。
大人によるいじめ
東京都産業労働局による、大人による職場でのいじめの定義は、以下のとおりです。
職場(職務を遂行する場所全て)において、仕事や人間関係で弱い立場に立たされている成員に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果として労働者の働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする行為(東京都産業労働局パンフレット内)
いじめの具体例

「学校(職場)の中で嫌な思いをしているが、これがいじめに当たるのかわからない…」
実際にいじめの被害に遭った人は、
「自分が被害的に考えすぎなのではないか」
「加害者は〝いじりだ〟と言っているので、自分が大げさに考えてはいけないのではないか」
と被害を我慢したり過小評価してしまうことがあります。
いじめに当たる行為は、どのようなものがあるのでしょうか。
以下、いじめの内容を具体的に説明します。
子どもによるいじめの場合
暴力によるいじめ
暴力によるいじめとは、殴る、平手で叩く、蹴る、わざとぶつかる、突き飛ばすなど、直接被害者の体に対して危害を加えるものです。
ひどい場合は、リンチのように一人の被害者に対して集団で暴力を振るう場合もあり、被害の程度が重大になります。
暴力によるいじめは、プロレスや遊びのふりをして行われる場合もあり、加害者が「じゃれあっていただけ」と言い張るケースも多いです。
そのため、周りの大人が「ただの遊びの延長」と思い込み、いじめに気付くのが遅れるケースは少なくありません。
強要するいじめ
強要するいじめとは、被害者が嫌がること、被害者を辱めること、被害者を危険に晒すことを強要することをいいます。
「金をたかる」「掃除当番を押し付ける」「荷物を持たせる」「奢らせる」「万引きをさせる」などの行為が該当します。
被害者が加害者の要求を拒むと、加害者は被害者に暴力を振るうなどの罰を与えるため、被害者は罰を受けることへの恐怖から、加害者に従わざるを得なくなってしまいます。
加害者は、自分の利益や面白さのためにいじめを行う傾向にあり、強要するいじめがエスカレートしていくと「人前で服を脱がされたり、脱ぐことを要求されたりする」といった深刻なケースに至ることもあります。
強要するいじめは、暴力を伴なわないものも多く、証拠が残りづらいことから、周囲の大人が気付きにくく、事態が深刻化してしまうこともあります。
言葉によるいじめ
言葉によるいじめとは、被害者が精神的に傷つく言葉を意図的に言ういじめです。
被害者の身体的特徴やコンプレックスを冷やかす、悪意のあるあだ名を付ける、陰口や脅し文句を言う、などが挙げられます。
始めは冗談のつもりだった〝からかい〟が徐々にエスカレートし、被害者の心を傷つけるいじめに発展する場合もあります。
こうした言葉によるいじめは、冗談のように言われることもあることから、被害者が「やめて」と訴えにくい傾向があり、事態が深刻化するまで周囲の大人が気付けないこともあります。
無視したり、仲間はずれにするいじめ
被害児童がまるでそこにいないものとして振る舞ういじめです。
無視や仲間はずれにされた被害者は、強い疎外感や孤立感を覚え、思い悩んでしまいます。
物を隠す・汚すいじめ
被害者の物を隠す、盗む、汚す、壊す、捨てるなどのいじめです。
被害者の教科書を破ったり、弁当を捨てたり、靴を隠したりするなどの被害を受ける場合があります。
インターネットを使ういじめ
LINEのグループから外す、被害者がいないグループチャットで悪口を言う、学校裏サイトなどの掲示板で悪口を言う、インターネット上で被害者の個人情報を拡散する、などの行為をいいます。
ネット内で行われるいじめは、大人が発見しにくいという特徴があり、いじめの温床となる危険性があります。
スマートフォンが普及し、子どもたちにとってもネット上の交流が浸透している現代において、SNSやネットでのいじめは特に問題視されています。
大人によるいじめの場合
暴言、暴力によるいじめ
職場の上司などから、殴る・蹴るなどの暴行を振るわれたり、仕事でミスをしたときに罵声を浴びせられるなどの行為をいいます。
また、他の社員の前で罵倒されたり辱められたりするなどの被害を受ける場合もあります。
無視・仲間外れ
挨拶を無視したり、話しかけても会話をしないなどの行為がこれにあたります。
被害者が一人で別室作業をさせられるなどの被害を受ける場合もあります。
過剰、過小な要求・業務指示
一人では到底こなすことのできない業務を与えることや、逆に、理由もなく能力に見合わない雑務のみしか任せないなどの行為をいいます。
その他のさまざまなハラスメント
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、モラルハラスメント、ジェンダーハラスメントなどのハラスメント行為も、職場内のいじめに該当します。
いじめの解決方法

いじめが発覚したとき、どのような対応を取れば良いのでしょうか。
いじめは、早期発見・早期介入が重要です。
放っておいて自然と改善されるものではないからです。
いじめの事実に気づいたら、勇気を持って解決のために行動することが大切でしょう。
学校や職場に報告し、調査・介入を求める
いじめが発覚したら、まずは学校や職場の相談窓口に連絡しましょう。
学校や職場は、いじめに関する通報があった場合には、いじめの調査をする義務があります。
学校や職場にいじめの調査や改善を求め、その結果を報告してもらいましょう。
学校・職場外の相談窓口に相談する
国や自治体、民間団体などが運営するいじめの相談窓口に相談する方法もあります。
子どもによるいじめの場合、NPO法人が運営するいじめ相談ホットラインや、法務省が運営する子どもの人権110番、文部科学省が運営する24時間子供SOSダイヤルなどで、いじめに関する相談を受け付けています。
大人によるいじめの場合、労働局や労働基準監督署の相談窓口、法務省の人権相談窓口、厚生労働省の総合労働相談コーナーなどで職場内でのいじめに関する相談を受け付けています。
法的措置を検討する
学校や教育委員会、職場の対応が不十分な場合は、法的措置を検討しましょう。
いじめは不法行為に当たるため、いじめを受けた児童・生徒は、加害児童・生徒に対して、自らが被った精神的・身体的損害に対する賠償を求める民事訴訟を起こすこともできます。
また、いじめが犯罪行為に該当するほど悪質な場合は、刑事告訴をすることもできます。
法的措置にあたっては、弁護士に相談することで、法的な観点から解決策をアドバイスしてもらえます。ま
た、弁護士が被害者の代理人として対応することで、学校や職場側にいじめ問題への対応をしっかりとしてもらうことが期待できます。
いじめの解決には証拠収集が重要

いじめの事実認定の段階で、学校や職場、加害者との間で争いになる場合も考えられます。
そんなとき、いじめを裏付ける客観的な証拠があると、より確実にいじめを立証でき、交渉を有利に進めることができます。
いじめの証拠として効果的なものは、以下の6つのとおりです。
1.いじめの経緯や内容を文書にしたもの
加害者からのいじめや嫌がらせの具体的な内容や、それらが起きた日時などを整理して文書として残したものは、いじめがあった証拠として扱われる可能性が高いです。
2.写真・動画・音声のデータ
いじめの現場を撮影、録音したものがあれば、決定的な証拠となります。
また、暴力を受けた際の怪我の写真を残しておくと、証拠として利用できます。
3.壊された物や汚された物
いじめの中で壊されたり汚されたりした物があれば、捨てずに証拠として保管しましょう。
4.被害者本人が書いた日記
いじめを受けた当時の被害者のリアルな感情が記載された日記は、いじめの証拠として扱われる可能性が高いです。
5.友人や同僚などの証言
いじめの現場を見たことがある、加害者が被害者の悪口や陰口を言っていたのを聞いたことがある、といった周囲の人の証言は、いじめの証拠となり得ます。
6.医師の診断書
暴力によるいじめを受けた際は、病院を受診して医師による診断書をもらうことで、暴力の客観的な証拠となります。
いじめの証拠収集は探偵への依頼が有効

いじめ被害の証拠を収集する際は、探偵に依頼することをお勧めします。
探偵に依頼することで、以下のような証拠収集を代行・サポートをしてもらえます。
学校や塾以外の場所での子どもの行動を把握する
子どもが学校や塾を出た後、帰宅中にいじめや嫌がらせを受けている場合もあります。
探偵が通学路や帰路での子どもの様子を見守り、いじめや嫌がらせの現場を写真や動画で撮影して証拠として保存することができます。
SNSなどのインターネット内でのいじめを調査する
SNSやネットの中でいじめを受けている場合、被害者への悪口の書き込みなどの画像をスクリーンショットなどで保存しておくことが重要です。
探偵は、被害者が実際に使っているSNSはもちろん、被害者の周囲の人間のSNSなどにもいじめに関する痕跡がないか細かくチェックし、ネット上のいじめの証拠をくまなく探し出すことができます。
録音などの証拠収集をプロがサポート
いじめは、学校や会社などの中で行われることが大半のため、尾行や張り込みをすることができません。
そこで、被害者本人による音声録音が重要な証拠となります。
スマートフォンの録音アプリや市販のボイスレコーダーでも録音することはできますが、捜査知識や経験のない人がそうした録音を試みるのは、正確に録音できなかったり、相手にばれる可能性があり危険です。
探偵に依頼することで、プロが使用するボイスレコーダーなどの録音機を貸し出したり、装着場所などのアドバイスを受けることができ、安心・確実な証拠取得が期待できます。
聞き込み調査により目撃証言を得る
探偵であれば、被害者の周囲の人間への聞き込み調査によって証拠収集することもできます。
いじめの目撃者は、自分の立場が危うくなることをおそれて、所属している学校や職場の調査に対して真実を話せない場合もあります。
しかし、探偵であれば、そうした目撃者の立場を考慮しつつ聞き込み調査を行えるため、多くの目撃証言を収集することが期待できます。
加害者が過去にも常習的にいじめ行為を行っていた場合は、過去の被害者たちに協力を頼み、同じような被害の証言を確保することもできます。
いじめでお悩みの方は当社にご相談ください

いじめの証拠収集を探偵に依頼する最大のメリットは、証拠収集の際の精神的な負担を軽減できることです。
いじめの被害を受けた人やその家族は、大きな心の傷を負っています。
そんな中で、無理をしていじめの証拠収集をしようとすると、最悪の場合、二次被害を受けてしまう可能性があります。
プロの探偵に証拠収集を依頼することで、被害者本人やその家族の心を守ることにもつながるのです。
当社では、いじめ被害に関するさまざまなご相談をお受けしております。
いじめについてお悩みの方は、まずはご相談だけでも、お気軽にご連絡ください。
ご相談は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間お受けしています。
問い合わせフォーム



