
政府が行った2023年の統計によると、国際結婚をしたのは18,475件、国際結婚からの離婚をしたのは8,772人でした。
日本人同士の結婚では、「3組に1組」が離婚をすると言われていますが、国際結婚の場合はその割合をも超えるということです。
しかし、国際結婚から離婚をするのは、手続きが複雑で難しいことが多くあります。
この記事では、国際結婚からの離婚で後悔しないためのポイントと、離婚手順を解説していきます。
また、離婚をスムーズに進めるための行動についても、くわしくお伝えしていきます。
国際結婚からの離婚を難しくする要因とは

国際結婚からの離婚を難しくする要因は、大きく分けて3つあります。
法律の壁
国際離婚の手続きを行う際に、まず問題になるのは、日本の裁判所に管轄権(どの機関や裁判所が責任を持ち、権限を行使できるかを示す権利のこと)が認められるか、そもそも日本の裁判所で扱えるのかということです。
日本に管轄権が認められるのは次のような場合です。
-
相手方の住所地が日本国内にあるとき
-
当事者双方が日本国籍を有するとき
-
当事者双方の最後の共通の住所地及び、原告の住所地が日本国内にあるとき
-
原告の住所地が日本国内にある場合であって
-
- i 被告が行方不明なとき
- ii 被告の住所地のある国においてなされた離婚裁判の確定判決が、日本で効力を有しないとき
- iii その他日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者の衡平(こうへい)を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められたとき
日本の管轄権が認められた場合、次に検討すべきは準拠法(どの国の法律を適用するかということ)の問題です。
日本の法律が適用されるケースは以下の通りです。
- 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である
- 夫婦の双方が日本に常居所を持つ
- 婚姻関係において、日本が最も密接な関係を持っている
一方、外国法が適用されるのは以下のようなケースです。
- 夫婦がともに外国に常居所を有している
- 夫婦の生活の本拠が明確に海外にある
つまり、日本で管轄権が認められたとしても、準拠法が外国法になった場合、日本の裁判所においてアメリカ法を適用して判断するという自体が生じることもあります。
言語の壁
国際離婚において、言語の壁は高いものです。
離婚協議における法律用語の違いや、法的書類の翻訳の必要性と正確性が求められた場合の対応など、お互いに齟齬がないように対話をするには時間がかかります。
言語が違うことによって考えられるリスクは、3つあります。
-
法律用語の理解不足:離婚手続きに関する複雑な法律用語を理解できないため、自分の権利や義務を十分に把握できない
-
翻訳の不正確さ: 重要な書類の翻訳が不正確であった場合、不利な条件で合意してしまうリスクがある
-
感情的な対立の激化: 離婚協議は、感情的になりやすい場面ですが、言語の壁があると、相手の言葉を誤解したり、自分の感情をうまく伝えられなかったりして、対立がさらに激化する
離婚協議は、精神的にも経済的にも大きな負担となりますが、言語の壁はその負担をさらに増大させ、長期化させる要因にもなります。
また、子どもへの影響も考えられます。
離婚後、どちらの言語を主に使うか、どちらの国の文化で育てるかを決めるのは難しいでしょう。
親が子どもの言語を理解できない場合も考えられます。
そういった場合、子どもの気持ちを理解することが難しく、親子のコミュニケーション不足が生じてしまいます。
親権問題の複雑化
日本の民法では離婚をすると、父親か母親の単独親権になると定められています。
しかし、国際離婚の場合は、どこの国で裁判を行うのかということと、どこの法律が適用されるのかによって親権の決め方が異なります。
つまり、日本に管轄権があったとしても、親権者を判断する際に、日本の法律が適用されるとは限りません。
この場合、子どもの本国法(その人の国籍国の法律のこと)が父母の一方の本国法と同一の場合か、その他の場合で異なります。
〇子どもの本国法が父母の一方と同一の場合
このケースでは、子どもの本国法が適用されます。
例えば、父が韓国国籍、母が日本国籍、子どもが日本国籍の場合は、日本の法律が適用されるということです。
〇その他の場合
子どもの本国法が父母と同一ではない場合は、子どもの常居所地法が適用されます。
常居所とは、人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり、相当期間にわたって居住する場所を指します。
裁判では居住期間だけでなく、居住の目的や居住の状況等を総合判断します。
例をあげると、父が日本国籍、母がアメリカ国籍、子どもがフランス国籍で、この常居所地が日本の場合は日本の法律が適用されることになります。
海外では共同親権を採用している国もあるため、準拠法によっては、日本とは違う制度に戸惑うこともあるでしょう。
国際離婚前に確認・準備すべきこと

国際結婚からの離婚をするためには、多くのハードルを越えなければならないことがわかったところで、離婚前にできることを確認しておきましょう。
法的準備
-
離婚手続きの流れの把握
-
国際離婚に強い弁護士の選定
-
必要書類の準備(戸籍謄本、婚姻証明書、財産に関する資料など)
前述したとおり、どの裁判所で、どの国の法律が行使されるかは、そのご家庭によって変わります。
自身がどういったケースに当てはまるのか確認をし、必要書類をまとめておくことで、弁護士への依頼もスムーズになります。
離婚後の生活設計
-
経済的な自立計画(仕事、住居、生活費など)
-
精神的なサポート体制の構築(友人、家族、カウンセラー)
-
母国へ帰国する場合の準備(ビザ、住居、仕事、保険など)
国際結婚からの離婚協議は複雑化しやすいため、通常の離婚協議よりも長引く可能性が高いです。
そのため、精神的にまいってしまうことも。
離婚が成立してからもろもろの手続きをするのではなく、事前に備えることで負担を減らすことに繋がります。
子どもがいる場合
-
子どもへの説明
-
親権、養育費、面会交流に関する取り決め
-
子どもの精神的なケア
子どもがいる場合、養育費・面会交流についての取り決めも重要です。
国際結婚からの離婚の場合、養育費が支払われなくなるケースも多発しており、養育費の支払い義務をはっきりさせるとともに、不払いに対する対策も講じる必要があります。
面会交流については、子どもの意志を尊重することが大切であり、面会交流の方法(ビデオ通話、手紙、直接面会など)や、面会交流の実施を妨害された場合の対応も考えておきましょう。
また、子どもを勝手に海外に連れ去ってしまうのを抑止するため締結された、ハーグ条約についても知っておく必要があります。
ハーグ条約の正式名は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」といいます。
国境を越えて子どもが不法に連れ去られたり、不法に留め置かれた場合に、子どもを元の居住国に変換する手続き、および、国境を越えた親子の面会交流を実現するための締結国間の協力などについて定めた条約です。
締結国は日本を含め103ヶ国(2024年8月1日時点)。
子どもを日本以外の条約締約国へ連れ去られたり、面会交流を阻まれてしまった親は、外務大臣に対して申請を行うことができます。
離婚手続きの具体的なステップ

離婚のための準備ができたところで、離婚手続きの具体的なステップを見ていきます。
1,協議離婚
夫婦で話し合い、離婚に合意する方法です。
離婚届を役所に提出すれば、2人の離婚は成立します。
ただし、両方の国で婚姻が成立している場合は、離婚手続きを夫婦双方の国で行う必要があります。
日本だけで届け出をして、配偶者の母国に届けを出さなければ、そちらでは「婚姻」したままの状態になってしまいます。
また、国によっては大使館・総領事館にも書類を提出する場合があります。
2,調停離婚
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停離婚を申し立てます。
調停離婚は、二人の間に裁判所が入り、離婚が適切か判断してもらう方法です。
DVなどで相手と顔を合わせるのが怖い場合でも、調停委員が間に入って話し合うため、直接顔を合わせる心配がありません。
ただし、強制力はなく、あくまで話し合いの場になります。
また、調停委員は公平な立場で話し合いを進めますが、必ずしも法的な専門家ではありません。
そのため、複雑な財産分与や親権問題では、専門的なアドバイスが得られない場合もあります。
3,審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所が調停に代わって離婚を成立させる、例外的な手続きです。
審判離婚が利用されるのは、以下のようなケースです。
-
どちらかが外国人で、自国に戻る予定がある(裁判所の判断による離婚しか認めていない国もあるため)
-
離婚することには納得しているが、離婚条件に関する意見の食い違いで調停不成立となった
-
子どもの親権を早く決めた方がいい状況にある
-
病気などの理由からどちらかが調停成立時に出席できず、調停不成立となった
確定した審判は裁判を行って確定した判決と同じ効力を有することになり、審判で決まった内容(慰謝料や養育費に支払い等)が守られないときは強制執行を申し立てることができます。
ただし、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内であれば、異議申し立てをすることができ、その場合審判は無効になります。
4,裁判離婚
「配偶者が頑なに離婚を拒否している」、「いつまで経っても話し合いが平行線で、このままでは離婚できないのではないか」といったケースは、家庭裁判所に対して離婚裁判を提起する必要があります。
裁判で離婚を認めてもらうという方法です。
この方法は、調停を経てからの手続きでないと認められません。
また、裁判離婚では民法で定められた離婚原因(不貞行為など)が必要になり、離婚を求める側は法律上の離婚原因が存在することを主張します。
そのためには証拠を提示して、離婚原因があることを証明していく必要があります。
国際結婚からの離婚をスムーズに進めるために
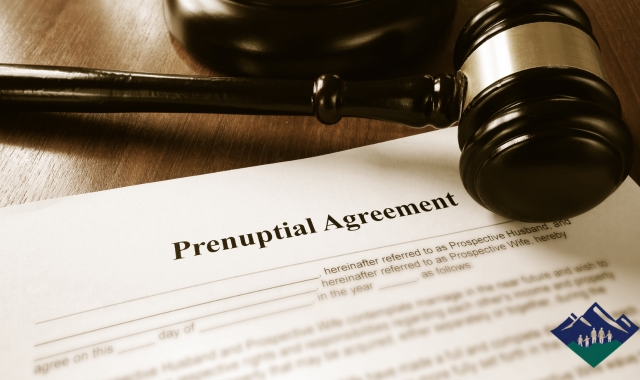
ここまで解説してきた通り、国際結婚からの離婚手続きは複雑です。
そこで、ここからは少しでも離婚をスムーズに進めるための方法を解説していきます。
結婚前に婚前契約書(プレナップ)を作っておく
婚前契約書(プレナップ)とは結婚をする前に、主に財産や資産についての取り決めを文書化して、ルールとして定めておく契約書のこと。
国際結婚で、どちらの国の法律に従うかトラブルが予想される場合に効果的です。
以下のような事項を定めるのが一般的になります。
- 財産・資産の取り扱いに関するルール
- 離婚時の財産分与の取り決め
- その他の離婚条件(親権・面会交流・養育費・慰謝料など)
- 夫婦生活における義務やルール、禁止事項
- 夫婦生活におけるルール違反のペナルティ(不倫・DV・モラハラなど)
婚前契約書(プレナップ)を作成するときの注意点としては、日本語のみで作成しないことと、公正証書化しておくことです。
公正証書は、公証役場で作成される公文書のことです。
「強制執行認諾文言」を付けることで、契約にもとづく金銭請求について、裁判を経ずに強制執行(財産差押え)を可能にする効力があります。
つまり、パートナーが公正証書の内容に従わなかったとき、金銭請求権については、裁判所に申し立てて強制的に実現させることができるのです。
弁護士に依頼する
とはいえ、婚前契約書(プレナップ)という文化が浸透していない日本では、作成していない場合もあるでしょう。
そういったときは専門家の力を借りましょう。
弁護士であれば、以下のようなことにも対応してくれます。
- 準拠法の確認
- 適切な手続き方法の選択
- 離婚届や必要書類の作成支援
- 子どもの親権や養育費に関する取り決め
- 財産分与の交渉、手続き
- 在留資格に関する相談
特に財産分与に関しては、海外にある資産も含めて検討する必要があります。
不動産や年金など、国をまたぐ資産については、各国の法制度を確認しなければならないため、サポートしてもらうのがおすすめです。
海外案件に強い探偵に依頼する
慰謝料請求や裁判離婚をする場合は、探偵に依頼することで、証拠集めを代行してもらえます。
前述したとおり、裁判離婚をするためには不貞行為など民法で定められた離婚原因が必要になります。
離婚手続きだけでも手いっぱいなのに、裁判所に認めてもらえるような証拠を自分ひとりで集めることは難しいでしょう。
客観的かつ確実な情報を提示するために、探偵に依頼することをおすすめします。
また、探偵は配偶者に不審に思われないよう巧みに情報収集をする術を持っているため、違和感なく調査することができます。
後悔のない離婚にするために、ぜひ一度ご相談ください

政府の統計からもわかるように、国際結婚からの離婚は決して珍しいことではありません。
しかし、日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚特有の大きな要因が立ちはだかり、その手続きは非常に複雑で困難を極めます。
国際結婚からの離婚は、確かに多くのハードルを伴います。しかし、その困難さを理解し、適切な知識と専門家のサポートを得てのぞむことで、後悔のない形で新たな人生の扉を開くことができます。
この複雑な道を乗り越え、あなたらしい未来を築いていくための第一歩を踏み出してください。





