
「相続の手続きを進めたいのに相続人が見つからない」「戸籍が途切れてしまった」
そんな悩みから、相続そのものが止まってしまうことがあります。
相続人のうち、誰かひとりでも所在が不明の人がいると、遺産分割協議(遺産を分けるために相続人全員で行う話し合いのこと)が無効になってしまうからです。
相続人の調査は、戸籍や住民票を取り寄せるだけでなく、場合によっては疎遠な家族との関係性や過去の居住歴、法律上の手続きまで踏み込んで確認する必要があります。
この記事では、相続人が見つからないときの対応方法から、調査の流れ・注意点、戸籍で追えないケースの対処法まで、相続手続きのポイントについて解説しています。
家族のことだからといって自分たちで何とかしようと思い込まず、必要に応じて第三者に頼ることも、円滑な相続には大切です。
相続人調査の基本的な流れと注意点

相続人の調査は、戸籍をたどるだけで完了するように見えて、実は思わぬ落とし穴や見落としが多い手続きです。
誰が相続人にあたるのか、どこまで調べれば十分なのか――。
こうした情報の整理こそが、スムーズな相続の第一歩になります。
以下では、相続人に関する基本知識から、調査の流れ、注意点や戸籍を読み解く際にありがちな誤解について、気をつけておきたいポイントをまとめています。
相続人の基本知識
相続人とは、亡くなった方の財産や権利・義務を引き継ぐ立場にある人を指します。
相続人の範囲は民法で決められており、誰が、どのくらいの割合で相続するかも、ある程度は法律で定められています。
まず基本として、配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人には順位があり、その順に応じて、誰が相続に関与するかが決まります。
以下は主なパターンと法定相続分の一例です。
| 相続人の組み合わせ | 相続人の順位 | 法定相続分の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども(実子・養子) | 第1順位 | 配偶者1/2、子ども1/2 |
| 配偶者と父母(または祖父母) | 第2順位 | 配偶者2/3、父母1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 第3順位 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
| 配偶者のみ | ― | 配偶者が全て相続 |
| 子どものみ(配偶者なし) | 第1順位 | 子ども全員で均等に分ける |
ですが、実際には、相続人の特定そのものが難しい以下のようなケースも少なくありません。
- 故人が再婚していたが、前婚の子どもの存在は家族が知らなかった
- 養子縁組していたが疎遠で、相続人として扱うべきか不明
- 非嫡出子(婚外子)がいたが、認知されたかどうかが不明
- 子どもが先に亡くなっていて、孫に代襲相続が発生している
- 戸籍が途切れていて、それ以上追えない状況になっている
このように、戸籍を見るだけでは見えてこない家族関係が絡むケースでは、相続人の調査そのものがとても重要になります。
正確に調査しないまま遺産分割を進めてしまうと、後から本来の相続人が判明し、トラブルに発展するおそれもあるのです。
戸籍調査の流れと取得方法
相続人を特定するには、まず誰が法定相続人になるのかを戸籍をもとに確認する必要があります。
戸籍には出生・婚姻・離婚・死亡・養子縁組などの情報が記載されており、家族関係の証明書として最も信頼できる資料です。
相続人調査における戸籍取得の流れは、以下のようになります。
- 被相続人(亡くなった方)の現在の戸籍(除籍)を取得する
└ まずは死亡時点の戸籍を取り寄せる。 - 過去の本籍地をたどって戸籍をさかのぼる
└ 結婚・転籍などで本籍地が移っている場合があるため、出生時までさかのぼって取得。 - 相続人に関係する戸籍を集める
└ 子どもや兄弟姉妹など、関係者の戸籍(現在の戸籍や除籍謄本)も確認。 - 取得した戸籍から家族構成を読み解く
└ 誰が相続人に該当するか、法的な関係性を確認する。
戸籍は基本的に本籍地の市区町村役場で取得します。
ただし、本人以外が取得する場合は委任状が必要になることもあるため、どの戸籍が必要で、どこに請求すればいいかを事前に整理しておくことが大切です。
戸籍をたどる作業は、どこまでさかのぼるかの判断が難しく、過去に複数回転籍している場合などは、調査が非常に煩雑になることもあります。
この段階で調査に行き詰まったり、思わぬ相続人の存在に気づいたりするケースも少なくありません。
調査を進めるときの注意点
相続人の調査は、戸籍を集めるだけで終わるものではありません。
集めた情報を正しく読み解き、適切に対応できるかどうかが、相続手続きを進めるカギになります。
しかし、実際に調査を進めるなかで、以下のようなポイントでつまずくケースがあります。
- 本籍地が何度も変わっていると戸籍の追跡が複雑になる
- 婚姻歴や離婚歴、認知・養子縁組などの情報が見落とされがち
- 相続放棄や失踪宣告などで「いるはずの人」が相続人でない場合もある
- 戸籍の読み間違いによる誤認
加えて、相続人を確定するうえでは、遺言書があるかどうかも重要な確認ポイントです。
内容や形式によっては法的効力に影響するため、遺言書が見つかった場合には、その有効性についても注意が必要です。
調査を進める際は、思い込みや先入観にとらわれず、客観的な事実にもとづいて判断する姿勢が求められます。
戸籍を読み解くときの注意点
戸籍は、相続人を特定するうえで最も基本的な資料ですが、形式的な記載に慣れていないと、重要な情報を見落としてしまうこともあります。
以下のようなポイントに注意しながら、戸籍の記載内容を正確に読み取ることが重要です。
- 読み間違いや勘違いによる誤認
例:同姓同名の人物を混同してしまう/婚姻・離婚歴を見落とす - 代襲相続に関する記載の解釈ミス
子が先に亡くなっていた場合は、孫に相続権が移るが、記載が複雑で見落とされるケースがある - 認知された子や養子などが明記されているかの確認
婚外子や養子縁組の記録が、戸籍に反映されていない・わかりにくい場合がある - 相続放棄や失踪宣告など、法的な判断が記載されていないこともある
戸籍だけでは相続権があるかどうかを判断できない場合もある
戸籍の記載は時代や改製によって表記の仕方が異なることもあるため、読み解くのに不安がある場合は、専門的な知識を持つ第三者のサポートを検討するのも一つの手段です。
相続人が多いケースや、家族構成が複雑な場合は、早めの相談がスムーズな相続につながります。
戸籍で追えない相続人のケースと対応方法

戸籍をたどれば相続人がすべてわかると考えている人も少なくありませんが、現実はそう簡単ではありません。
戸籍だけでは相続人の全容を把握できないケースは、意外と多くあるのです。
以下では、戸籍で追いきれない相続人がどういったケースで発生するのか、調査を依頼する際の準備などを整理します。
行方不明・疎遠な相続人
相続人のなかには、長年連絡を取っていない人や、現在どこに住んでいるのかがわからない人がいるケースは、実際の相続手続きでも珍しくありません。
相続は原則として、相続人全員の合意によって進める必要があるため、ひとりでも所在不明の相続人がいると、遺産分割協議が止まってしまうリスクがあります。
よくある事例としては、以下のようなパターンが挙げられます。
- 兄弟姉妹で長年絶縁状態にあり、連絡先がわからない
- 高齢の親族が施設や病院に入所しており、所在の手がかりがない
- 海外に移住しているが、戸籍には国外転出の記載があるだけ
- 前の結婚で生まれた子どもと数十年音信不通になっている
- 転居を繰り返していて、住民票の履歴も途中で途切れている
こうしたケースでは、戸籍や住民票を取り寄せても現在の所在がわからず、自力で探すのが難しい状況に陥ることもあります。
このような場合は、調査のプロである探偵事務所などに協力を仰ぎ、相手の居住地や連絡先を特定したうえで、相続の意思確認や協議に進む必要があります。
婚外子・養子などの相続人
相続人のなかには、婚外子(非嫡出子)や養子といった戸籍を確認しただけでは存在に気づきにくい相続人もいます。
たとえば、故人が過去に認知した子どもがいた場合、その子は法律上の相続人となりますが、関係者のあいだでその存在自体が共有されていないこともあります。
加えて、戸籍の情報は必ずしも最新の家族関係を網羅しているわけではありません。
以下のような事情で、現在の戸籍だけでは相続人の特定が難しくなることもあります。
- 養子が養親と別の本籍地に転籍していた
- 婚外子が分籍しており、直近の戸籍に記載されていない
- 戸籍の改製により、旧情報が除籍簿へ移動している
こうした相続人の存在に気づかずに手続きを進めてしまうと、後から遺産分割のやり直しや無効を主張されるリスクも発生します。
とくに、家庭環境が複雑だったり、前妻・前夫との間に子どもがいるような場合には、戸籍を一通り確認しただけで安心せず、可能性のある人物を丁寧に洗い出す姿勢が大切です。
制度で対応できるケース
相続人の所在がわからない、連絡がつかないといった場合でも、すべてを調査だけで解決する必要はありません。
状況によっては、以下のような法律上の制度を利用して対応できるケースもあります。
相続放棄
相続人が財産を受け取らない意思を示す制度で、家庭裁判所への申立てが必要。
相続人がすでに放棄しているかどうかは、戸籍や関係者への聞き取りで確認できる場合もある。
失踪宣告
行方不明になって7年以上経過している場合、その人を法律上死亡したとみなせる制度。
家庭裁判所へ申立て、裁判所が認めれば相続手続きを進められる。
不在者財産管理人の選任
相続人と連絡がつかず協議が進められないとき、その人の代理として話し合いに参加できる。
不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てることが可能。
これらの制度を使えば、相続人全員と直接連絡が取れなくても、一定の法的プロセスを踏んで相続を進めることが可能です。
状況ごとに判断基準の目安を挙げると以下のようになります。
- すでに「相続放棄した」と伝えられている → 相続放棄の確認
- 7年以上音信不通で消息不明 → 失踪宣告の検討
- 連絡はつかないが死亡しているとはいえない → 不在者財産管理人の選任
ただし、どの制度を利用するかの判断には法的な知識が必要な場合もあるため、状況に応じて弁護士や司法書士への相談も視野に入れるとよいでしょう。
調査依頼の前に準備しておきたい情報
相続人の所在がわからず、調査を依頼する場合には、あらかじめ一定の情報を整理しておくことで、調査をスムーズに進めやすくなります。
具体的には、以下のような情報があると有効です。
- 最新の戸籍の写し〜可能な限り最新のもの
- 家族構成や関係性を示すメモ〜親族関係を時系列でまとめたもの(例:前妻との子、認知した子など)、疎遠になった理由や関係性も調査のヒントになる
- 過去の居住地・勤務先・学歴など
- 生年月日や婚姻歴などの基本情報〜同姓同名の人物との混同を避けるため
このような情報を事前に整理しておくことで、調査の精度が上がるだけでなく、調査期間や費用の軽減にもつながる可能性があります。
調査の相談する際は、何をどこまで知っているかを正直に共有することが、最終的に納得のいく結果を得るための第一歩となります。
相続人が見つからないときの対応方法

相続手続きを進める際に相続人と長年連絡を取っていない、関係がこじれていて連絡を取りたくないなど、相続人同士が協力しにくいケースも多くあります。
こうした状況では、相続そのものが止まってしまうこともあり、時間が経つほど話し合いは難しくなりがちです。
以下では、相続人が見つからないときに何が問題となるのか、関わりたくないと感じる相手がいるときにどんな対応が考えられるかなどについて解説していきます。
相続手続きが進まない理由とは
相続手続きは、誰か一人でも所在がわからない・連絡が取れない・話し合いに応じないといった状況があると、手続きは中断されてしまいます。
特に問題になりやすいのは、次のようなケースです。
- 相続人の一部と音信不通で、連絡手段がない
- 相続に関する通知を送っても反応がない
- 明確に「相続に関わりたくない」と拒否される
- 相続放棄の意思があるが、手続きをしていない
- 家族関係のトラブルから、関わること自体が難しい
相続手続きが止まってしまうと、不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きも進められず、生活への影響が生じることもあります。
加えて、時間が経つことで関係性がさらに悪化し、感情的な対立や法的トラブルへと発展してしまうケースもあるのです。
相続人の協力が得られない状況を放置するのではなく、何が障壁になっているのかを整理し、現実的な対処法を検討することが大切です。
連絡を取りたくない相続人がいるときの悩みと選択肢
相続人全員での話し合いが必要とわかっていても、できることなら関わりたくないと感じる相手が含まれていることもあります。
たとえば以下のような関係性の場合です。
- 昔から折り合いが悪く、絶縁状態が続いている
- 家族内の暴力・モラハラなどの被害を受けた過去がある
- 金銭トラブルや借金を抱えていて信用できない
- 揉めごとになりそうで、連絡自体に強いストレスを感じる
こうした背景から連絡を避けてしまうのは、決してわがままではなく、過去の関係性や心の傷が影響している人にとって、ごく自然な感情です。
ですが、連絡を取らずに手続きを進めることは原則できないため、どうしても直接のやりとりが難しい場合は、以下の方法があります。
- 探偵を通じて、居場所や状況を調べる
- 弁護士に相談して、法的に中立な立場で連絡してもらう
- 相続放棄や不在者財産管理人などの制度を活用する
第三者を介した形での対応を考えるのが現実的です。
直接連絡を取らずとも進められる道もあるため、まずは落ち着いて選択肢を整理していくことが大切です。
放置していると起こりうるトラブル
相続人が見つからない、または関わりたくないという理由で相続手続きを後回しにしてしまうと、さまざまなトラブルが発生するおそれがあります。
代表的なリスクには、次のようなものがあります。
- 不動産の名義変更ができず、売却や利用が制限される
→ 名義人が故人のままだと、不動産を売却・賃貸することができません。 - 相続税の申告期限を過ぎてしまう
→ 相続税には申告・納付の期限(原則10か月)があり、遅れると延滞税が発生します。 - 他の相続人との関係が悪化する可能性がある
→ 誰か一人が手続きを止めていると、他の相続人から責められることも。家庭内で新たな火種になるケースもあります。 - 第三者に財産を持ち逃げされるリスクも
→ 銀行口座が名義変更されず放置されることで、不正引き出しなどのトラブルに発展するおそれがあります。
相続人調査を先延ばしにしても、問題が自然に解決することはほとんどありません。
不安な点がある場合は、早めに相談先を見つけることが、後悔しないための第一歩です。
頼れる相談窓口の選び方

相続人が見つからない場合、自分たちだけで調査を進めるのは限界があります。
戸籍や住民票だけでは情報が足りず、どう調べればいいのかわからないといったときこそ、適切な窓口に相談することが大切です。
以下では、相続人調査を相談できる代表的な機関や、状況に応じた選び方のポイントを解説します。
目的や状況に合った相談先を知ることで、スムーズに手続きを進める一歩が見えてきます。
相続人調査を相談できる主な窓口
相続人の調査は、戸籍や法律、現地調査など多方面の知識が関わるため、状況に応じて適切な窓口を選ぶことが重要です。
ここでは、相続人調査に関わる代表的な相談先と、それぞれの特徴を紹介します。
弁護士
相続放棄や失踪宣告など法的手続きが必要な場合に対応
相続トラブルの解決、遺産分割の交渉・調停も依頼可能
法的な強制力が必要なケースに強い
司法書士・行政書士
戸籍の取り寄せや家系図の作成など、書類関連の手続きを得意とする
家庭裁判所に提出する相続関連書類の作成を代行できる
法律相談は扱わないが、実務面での支援に強い
探偵事務所(調査会社)
戸籍では追いきれない行方不明・疎遠な相続人の所在調査が可能
過去の居住地や交友関係の調査など、実地調査を伴うケースに対応
家族に知られずに調査を進めたい場合にも配慮した対応ができる
家庭裁判所
相続放棄・限定承認・失踪宣告の申し立て先
行政では対応できない制度的な判断が必要なときに関与
書類の正確性や調査資料が必要となるため、法律家との連携が基本
市区町村(戸籍・住民票の窓口)
戸籍や住民票の取得はここからスタート
本籍地が遠方にある場合は郵送での請求も可能
相続人調査の第一歩として利用する人が多い
信託銀行・相続代行サービス
財産管理や相続手続きを一括して任せられるサービスもある
調査は外部に委託されるケースが多いため、実際の調査内容には限界も
忙しい方や高齢の方が利用するケースも見られる
このように、相続人調査には複数の相談先があります。
どこに相談するべきかは、相続の状況や家族関係、調査の目的によって異なります。
「どこから手をつければいいかわからない」と迷ったときは、複数の窓口に問い合わせて比較することも有効です。
状況別でみる相談先
相続人調査と一口にいっても、その背景や状況はさまざまです。
ここでは、よくあるケースごとに、どこに相談すればよいかを整理しました。
相続人が行方不明・連絡が取れない場合
戸籍には名前が記載されていても、住所や連絡先がわからないケースでは、探偵事務所による所在調査が有効です。
生死不明のまま時間が経っている場合、弁護士を通じて家庭裁判所に失踪宣告を申し立てるといった法的対応も検討されます。
戸籍が古くて読みにくい・取得に手間取っている場合
本籍地が遠方にある、改製原戸籍が必要になる、といったケースでは、司法書士や行政書士に戸籍の取得を依頼することも可能です。
特に複数の市区町村をまたぐ場合などは、取得手続きのプロに任せることで、スムーズに調査が進みます。
家族間のトラブルや絶縁があり、関わるのが難しい場合
「自分では連絡を取りたくない」「相手が拒絶している」といった事情があるときは、探偵事務所による非接触型の調査が有効です。
話し合いが必要な場面では、弁護士が間に入ることで、直接のやり取りを避けながら手続きを進めることができます。
相続手続きを丸ごと任せたい・高齢で手続きが困難な場合
一連の相続業務を一括でサポートしてほしい場合は、信託銀行や相続専門サービスの利用も視野に入ります。
ただし、調査の柔軟性や家族事情への配慮という点では、探偵事務所や法律家との連携が取れているかを確認することが大切です。
このように、状況によって相談先の適性は異なります。
自分に合った相談先がわからないという方も、まずは当調査事務所までご相談ください。
現在の状況やお悩みを丁寧に伺ったうえで、最適な調査方法や連携機関をご提案いたします。
当調査事務所でできること
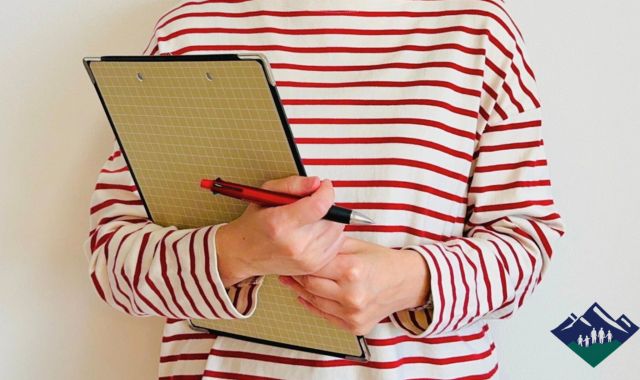
相続人の調査は、単に戸籍を集めるだけでは終わりません。
家族の事情が複雑な場合や、相続人が行方不明・海外在住・連絡拒否などの状態にあると、相続手続きを進めるうえで多くの壁に直面します。
当調査事務所では、そうした悩みを抱える方に向けて、以下のような多角的なサポートを提供しています。
居場所・連絡先の特定に関する調査
相続人の所在がわからない場合は、戸籍や住民票をたどっても最新の居住地にたどり着けないことがあります。
とくに、転居を繰り返している人や海外に居住しているケースでは、書類上の情報だけでは限界があります。
当調査事務所では、以下のような方法を組み合わせて、相続人の居場所を特定する調査を行っています。
- 旧住所周辺での聞き取り調査
- 勤務先・通学先など過去の生活拠点の追跡
- SNSやWeb上の公開情報の調査
- 不動産登記や電話番号の逆引き情報など公的データの活用
直接は接触せずに、居場所だけ知りたいといったご希望にも柔軟に対応可能です。
相続人の人物像・背景を把握するための信用調査
相続人が特定できても、その人物がどのような生活状況にあるのか、どんな性格・経済状況なのかが不透明なままでは、遺産分割協議に不安を感じる方も多いものです。
たとえば、相続人に借金癖があったり、浪費傾向が強かったりすると、他の相続人とのトラブルや財産管理の不安要素にもなりかねません。
当調査事務所では、合法的な範囲で以下のような項目を調査可能です。
- 居住環境や生活状況
- 職業・収入・借金などの経済背景
- 人柄・交友関係・SNS上の活動
- 金銭トラブルや訴訟歴、過去の破産情報
相続を誰と一緒に進めていくかに不安がある場合、こうした調査は非常に有効です。
トラブル回避のための連絡代行・意向確認
自分からは伝えづらい事情があるときは、第三者である調査事務所が間に入り、トラブルを避けて意向確認を進めることができます。
当事務所では、ご依頼者の意向に沿って以下のような対応が可能です。
- 相手への初回連絡の代行(書面・訪問・電話等)
- 相続の意思や話し合いの意向についての聞き取り
- 書面での通知や報告書の作成
- 必要に応じて弁護士・司法書士との連携
連絡手段や伝える内容は事前にすり合わせのうえ、慎重に対応いたします。
財産・負債の内容や相続関係の整理支援
相続人だけでなく、遺産そのものの中身も調査の対象となります。
財産が不明瞭なままでは、相続するか放棄するかの判断もつかないためです。
当調査事務所では、被相続人の財産状況に関して以下のような調査支援が可能です。
- 銀行口座・不動産・有価証券などの財産調査
- 借金・ローン・個人間の債務などの負債確認
- 信用情報機関(CIC・JICCなど)への照会サポート
- 戸籍調査結果をもとにした相続関係図の整理・作成
これらの情報を整理することで、相続放棄や分割協議の判断材料として活用できます。
相続人調査で悩んだ時はまず相談を

相続の手続きを進めるには、誰が相続人かを正確に把握し、全員と連絡が取れる状態でなければなりません。
ですが、行方不明の相続人がいたり、戸籍でたどれないケース、関わりたくない相続人がいるなど、思いどおりに進められない事情を抱えている方も少なくありません。
こうした状況を一人で抱え込んでしまうと、相続が何年も進まず、トラブルが長期化してしまうおそれもあります。
そんなときは、早めに外部の力を借りることも大切です。
当調査事務所では、相続人調査のご相談を随時受け付けており、状況に応じた対応方法や進め方をご提案できます。
まずはお話をうかがい、どんな選択肢があるかを一緒に整理するところから始めましょう。






